■ 叱る?守る?──その“分岐点”に立たされるあなたへ
部下やチームメンバーがミスをしたとき、
あなたはどう向き合っていますか?
- 強く叱って“けじめ”を示すべきか
- まずは寄り添い、共に問題に向き合うべきか
- 自分の立場を守るために距離を取るべきか
ミスの大小に関わらず、リーダーには「判断」が求められます。
叱るか、共に戦うか。
どちらの選択にもリスクと意味がある。
だからこそ、迷うのです。
■ 「叱ること」が悪いわけじゃない。ただ、そこに“理由”があるか
「叱る」という行為自体は、決して悪ではありません。
- 重大なミスを軽視してはいけない
- 再発防止のためにも、“責任”を明確にする必要がある
- チーム全体に「緊張感」を伝える意味もある
でも──その“叱責”は、誰のためのものですか?
● 怒ることで、自分の立場を守っていないか?
● ミスの責任を押し付けるような言い方になっていないか?
● 相手に“恐れ”だけを与えていないか?
叱ることが「育てること」になっていれば、それは正しい。
けれど、ただ“その場の怒り”をぶつけてしまったなら──
それは、あなた自身の信頼を削る行為になってしまうかもしれません。
■ 「一緒に行こうか?」──共闘の姿勢が生むもの
一方で、共に頭を下げる。
ミスの責任を自分ごととして一緒に受け止める。
それは、チームに安心感と“信頼の土壌”をもたらします。
- 落ち込む部下の支えになる
- 「見捨てられなかった」という経験が、その後の成長につながる
- チームに“守られている空気”が生まれる
でも──
この姿勢もまた、万能ではありません。
● 部下が責任を“上司任せ”にしてしまうこともある
● 他部署から「本人じゃなくて上司が謝っているだけ」と見られることもある
● 「やさしすぎるリーダー」と見なされ、緩みが生まれることもある
だからこそ、共闘を選ぶにも「判断」がいる。
それが、“信頼を育てる行動”になるかどうか──
その見極めが、リーダーに求められているのです。
■ リーダーに必要なのは「正解」じゃなく「感覚のバランス」
正解なんて、ありません。
マニュアル通りにいかないのが、人間関係です。
でも、だからこそリーダーは──
“何をどう受け止め、どう伝えるか”というバランス感覚を磨いていく必要がある。
- 叱責と共闘、その間にあるグラデーションを感じ取る
- 部下のタイプによって言葉を変える
- 「伝えたいこと」と「伝わる言い方」を一致させる努力
その柔軟さこそが、リーダーとしての信頼を積み重ねていく力になるんです。
■ まとめ|迷うからこそ、あなたはリーダーなのだ
ミスが起きたとき、リーダーが先頭に立って「何かを選ぶ」必要がある。
その選択に、絶対の正解はありません。
でも──
「迷った自分を信じる」ことが、チームに伝わることもあります。
叱るべきか?
共に頭を下げるべきか?
そのどちらも、チームの未来を考えているからこそ出る“迷い”です。
迷うことこそ、リーダーの証。
あなたのその判断に、きっとチームはついてきてくれます。
実際に「あなたの部下がやらかした」と突然言われたとき、どう動けばよいか──
Vol.3の記事では、そんな“初動判断”のリアルに迫っています。
👉 あなたの部下がやらかしました──その時、どう動く?
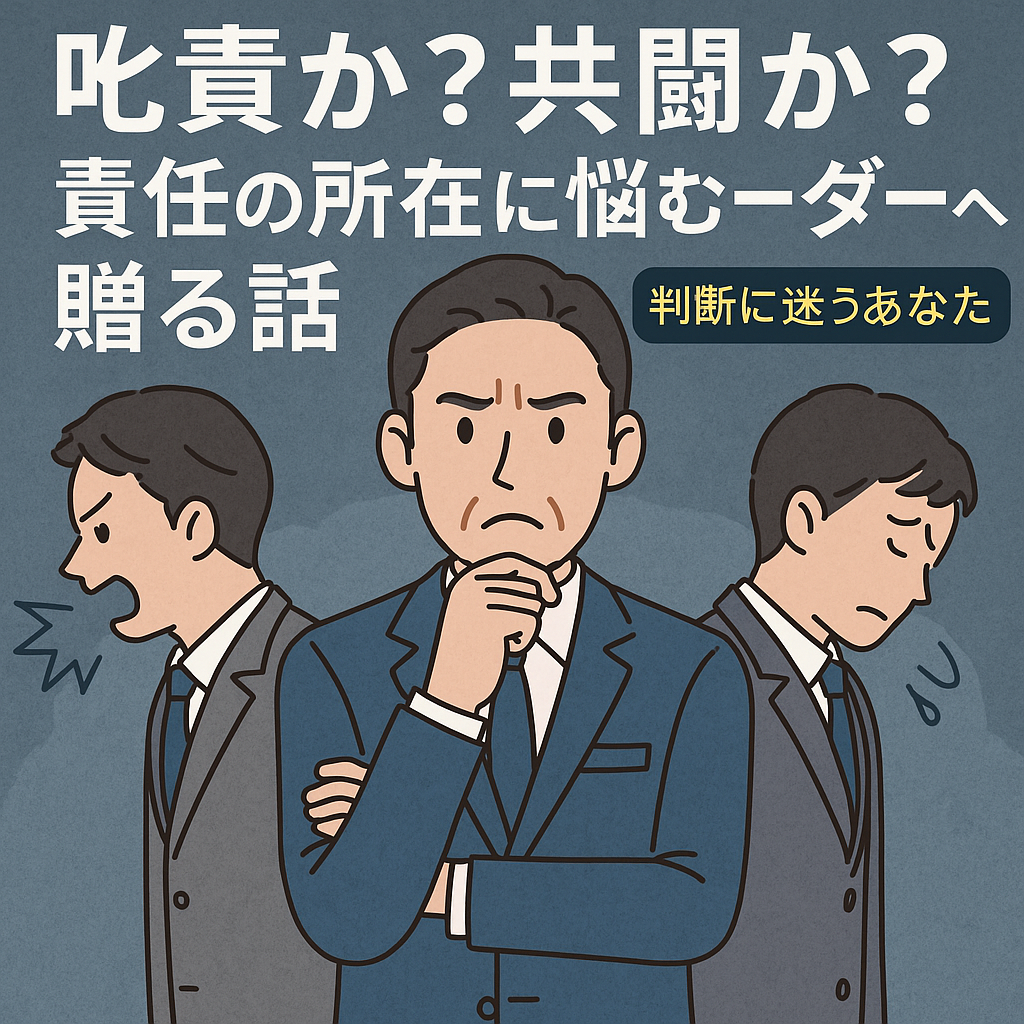

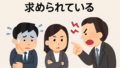
コメント