「えっ、3年経ったら終わりなの?」
せっかく見つけた心地いい職場も、“3年ルール”でさようなら?
今回はそんな「派遣の期間制限」の仕組みと、知っておきたい例外や選択肢をやさしく解説します。
【1】「期間制限」ってなに?──まずは制度の基本から
派遣として働くうえで、まず知っておきたいのが「期間制限」のルールです。
これは、同じ派遣先で働ける期間に上限があるという制度。
つまり、「居心地が良いからこの職場にずっといたいな〜」と思っても、
ずっとそのまま働き続けられるわけではないんです。
背景にあるのは、「派遣労働者の安定した雇用とキャリア形成を支援する」という考え方。
制度としては、同一の派遣先・同一の業務では最長3年までとされています。
【2】どうして3年なの?──その目的とルールの概要
この「3年」という期間は、派遣という働き方の特性と、労働者の保護を両立させるために設けられています。
ポイントは以下の通り:
- 同一の派遣先で
- 同一の業務内容に就く場合、
- 最長3年間までの就業が原則ルール。
仮に派遣元(派遣会社)を変えたとしても、派遣先が同じであればこの制限はリセットされません。
【3】実は“例外”もある?──3年を超えて働くには
実はこの「3年ルール」にも例外があります。
「もうすぐ3年、もう辞めなきゃいけないの?」と思うかもしれませんが、ケースによっては継続が可能です。
✅ 例外パターン:
- 派遣先が直接雇用として採用する場合
(契約社員や正社員など) - 部署異動によって業務内容が大きく変わった場合
(業務が“同一”でないと判断されれば再スタート) - 「抵触日通知」に基づく調整や延長の打診
派遣先企業から通知があり、手続きがなされていれば継続も可能なケースがあります。
いずれにしても、派遣元や派遣先とのコミュニケーションが大切です。
【4】いつからカウントされるの?──“開始日”と“対象業務”
この「3年」のカウントは、派遣先での初出勤日が起点となります。
週に数日だけの勤務でも、その初日から起算されます。
また、「業務内容の違い」がポイントになることもあります。
たとえば、事務職から軽作業に業務が切り替わった場合、それが“同一業務”に当たるかどうかでカウントが変わることも。
なお、登録型派遣と常用型派遣でも扱いが異なるため、自分の雇用形態を確認しておくことも大切です。
【5】気をつけたいポイント──期間制限が近づいてきたら
派遣で長く働いていると、「あれ、そろそろ3年?」と感じるタイミングが出てきます。
そのときに大事なのは、“放置しないこと”。
✅ チェックポイント:
- 派遣元(派遣会社)からの説明を受けているか?
- 「抵触日通知」や更新の有無について確認済みか?
- 自分の働き方に変化があるか(業務・部署の異動など)
もし今の職場での継続を希望するなら、早めに派遣会社へ相談するのがベストです!
【6】最後に…マリーさんからのやさしいエール
「派遣って、続けられないんだ…」
そんなふうに思ったとき、マリーさんはこう伝えたいの。
「終わり」じゃないよ、「次の選択肢の扉」が開いたサインなの🌱
あなたの人生を決めるのは、制度じゃなくて、あなた自身。
この3年ルールだって、未来の選択肢に気づく“きっかけ”になるはず。
だからこそ、知識を持って、自分の未来をじっくり描いていこうね✨
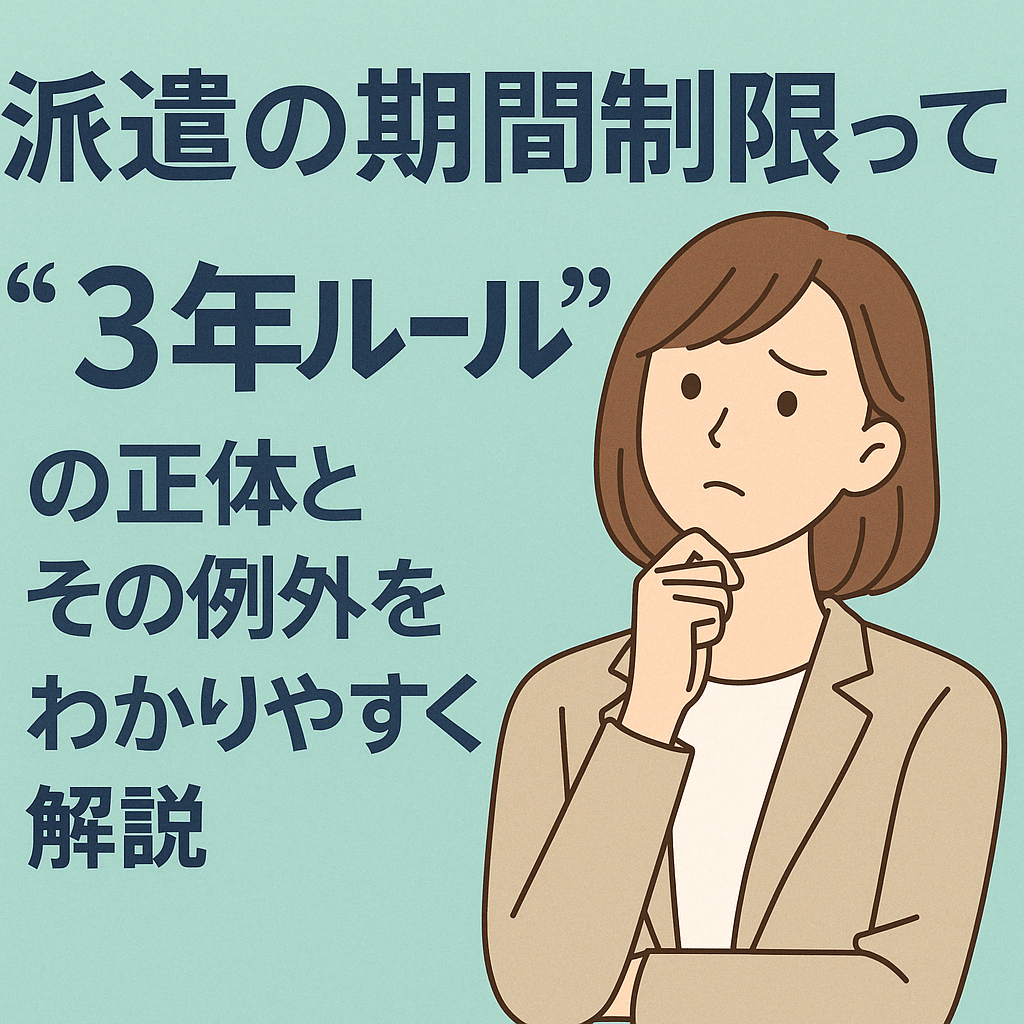


コメント